| 梛曄揤栚拑榪丂奣梫 |
|---|
梛曄揤栚拑榪偺傆傞偝偲乽寶梣乿偼丄拞崙偺暉寶徣偺杒晹丄尰嵼偺寶梲巗杒抂晹偺悈媑捔偺屻堜懞丄抮拞懞堦懷偵偁傞丅 尰嵼傑偱偵傕嶰廫悢婎偺梣愓偺挷嵏偑峴傢傟丄枹偩偵偦偺挷嵏偼宲懕偝傟偰偄傞丅 偙偙偱偼丄拞崙丄擔杮偵墬偗傞楌巎揑側愢柧偼嬌椡徣偒丄梛曄揤栚拑榪傗桘揌揤栚拑榪側偳寶梣惢摡婍偵娭偡傞悇嶡傪 峴偄偨偄丅 憊戙寶梣偺庡側惗嶻昳偼丄揺焲岬乮埲崀婰弎偼壯栚揤栚乯丄揌庫乮埲崀婰弎偼桘揌揤栚乯丄梛曄揤栚拑榪丄闥轶斄岬偱偁傞丅 崟缰偺暔偼梣曄尰徾偑尰傟側偐偭偨暔偱丄摉弶偐傜偦傟傪慱偭偰從惉偝傟偨暔偱偼側偄偲峫偊傜傟傞丅 闥轶斄岬偵娭偟偰偼彅愢偁傝丄寶梣惢昳慡斒傪巜偟帵偡尵梩偲偄偆愢傗丄崟缰偺忋偐傜恖堊揑偵敀偄缰栻傪斄栦忬偵暲傋偨 暔偩偗傪巜偟帵偡偲偄偆愢側偳偑偁傞偑丄偙偙偱偼偙偺帠偵尵媦偟偰傕巇曽偑側偄偲峫偊傞丅 傑偨丄闥轶斄岬偑桘揌傗梛曄傪柾偟偨暔偲偡傞愢傕偁傞偑丄偁傑傝偵抰愘側偱偒偱偁傝丄暿偵壗傜偐偺帠忣偑偁傞偲峫偊偨 曽偑椙偄偲巚傢傟傞丅 娙扨偵峫嶡偡傞偲偡傟偽丄奊晅偗偵埶傞敀偄斄栦偑拑榪偺撪懁偩偗偵偟偐昤偐傟偰偄側偄揰偵拲栚偡傟偽丄偙偺斄栦偑梛曄揤栚拑榪傪尒偨恖暔偵傛偭偰嶌傜傟偨壜擻惈偑偁傞丅 偁傑傝偵抰愘側昤夋偱偁傞堊偵偐偊偭偰敾抐偑撦傞偑丄捠忢偺峫偊偱偼榦偺奜懁偵傕斄栦傪昤偔応崌傕偁傞偱偁傠偆偑丄偙傟偑尒傜傟側偄偺偼丄栚偵偟偨梛曄揤栚拑榪偺柾曧傪嶌傠偆偲偟偨偲偟偰傕偍偐偟偔偼側偄偲巚偊偰偔傞丅 偟偐偟丄摗揷旤弍娰傗摉幮偺幚尡偱丄梛曄偺斄栦偼奜懁偵偼弌棃偵偔偄偩偗偱偁偭偰丄弌棃側偄栿偱偼側偄帠偑幚徹偝傟偰偄傞 傑偨丄焲曄岬偲偄偆缰挷偺婰弎偑拞崙偺暥專偵尒傜傟傞偑丄恖堊揑側柾條偲峫偊傜傟傞丅 闥轶偲偄偆捁偵娭偟偰偼丄僂僘儔偺堦庬偱偁傞偲尵傢傟丄庱偺曈傝偺柾條偑斄栦忬傪惉偟偰偄傞丅 丂丂丂丂丂  丂 丂  丂丂丂丂丂丂丂丂丂闥轶斄岬丠丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂闥轶丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂焲曄岬 惗嶻昳偺拞偱傕丄孮傪敳偄偰悢偑懡偄偺偑丄壯栚忬栦條偑尰傟偨乽壯栚揤栚乿偱偁傞丅 傑偨丄偙偺拞偱傕傎偲傫偳傪愯傔傞惢昳偼丄柧拑怓偺嬝忬偺壯栚揤栚偱偁傞偑丄栦條偑儔僗僞乕忬怓嵤傪懷傃傞傕偺偑丄 擔杮偺揱悽昳偵尒傜傟傞偑丄慡懱偐傜尒傟偽傎傫偺嬐偐側傕偺偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅 梛曄揤栚拑榪偵娭偟偰偼擔杮偵俁榦偩偗丄桘揌揤栚拑榪偵娭偟偰傕擔杮偵悢榦偲傾儊儕僇偺僼儕乕傾旤弍娰偺暔偑抦傜傟 傞掱搙偱偁傝丄悢検揑偵傕嬐偐側暔偑從偐傟偨偵堘偄側偄丅 壗屘丄偙傟偩偗偺桪昳偑婏柇側偔傜偄擔杮偵廤傑偭偰偄傞偐偲偄偆帠偵偮偄偰丄嬤戙偺尋媶偱偼丄杒憊帪戙偐傜撿憊帪戙 弶摢偵偐偗偰拞崙崙撪偱棳峴偟偨媔拑曽朄偲摤拑偺廗姷偑丄撿憊帪戙拞婜偵偼媔拑曽朄偍傛傃拑偺惢憿曽朄偑曄傢偭偨帠 偵傛偭偰丄寶岬偑懜偽傟側偔側傝丄偦偺崰偵擔杮偺媔拑偺棳峴偲偑偐偝側傝丄偄傢偽拞屆昳偲偟偰崅偔攧傟傞擔杮偵丄戝 検偵桝弌偝傟偨偲尵傢傟偰偄傞丅 尵偄曽偼埆偄偐傕偟傟側偄偑丄僐儞僺儏乕僞帪戙偵擔杮偑丄懠偺崙偑嶼斦傪崅妟偱攦偭偰偔傟傞偲尵傢傟偰丄戝検偵桝弌 偟偨傛偆側傕偺偐傕偟傟側偄丅 偲偼偄偊丄嬤偔偵偁傝奃旐揤栚傪惢憿偟偨拑梞梣傗丄媑廈梣偑敀偄搚偵傢偞傢偞崟搚偺壔徬傪偟偰崟缰拑榪傪從惉偟偰偄 傞張偐傜傕丄寶梣惢昳偑偄偐偵恖乆偵岲傑傟偰偄偨偺偐偼悇嶡偱偒傞丅 |
| 梛曄揤栚拑榪丂壯栚揤栚 |
| 嬤擭丄梛曄揤栚拑榪偑恖堊揑偵奊晅偗偝傟偨暔偱偁傞偲偄偆愢傪彞偊傞曽偑偄傜偭偟傖偭偨傝丄傑偨岞慠偲奊晅偗媄朄傪巊偄 乽梛曄揤栚拑榪偺嵞尰乿傪姰惉偝偣偨偐偺擛偔偺敪昞傪峴偄丄傑偨偼偦傟傪岞偺怴暦巻忋側偳偵宖嵹偡傞側偳偑峴傢傟偰偍傝 抦傞尷傝偱傕丄悢恖偺嶌壠偺曽偑偦傟傪偍偙側偭偰偄傞傛偆偱偁傞丅 傕偪傠傫丄俉侽侽擭埲忋傕慜偵弌棃偨拑榪偑偳偺傛偆側媄朄偵傛偭偰惗傑傟偨偺偐傪幚徹偡傞帠偼丄崲擄側帠偱偁傝丄尰暔偺 旕攋夡帋尡偱傕嫋偝傟傞帪傪懸偨偹偽側傜側偄偐傕偟傟側偄偑丄偁傞掱搙偼巆偝傟偨寶岬偲丄偦傟傪娤嶡偡傞帠偱悇嶡偡傞帠 偼壜擻偱偁傞偲峫偊傞丅 偁傞丄嶌壠偺曽偼丄嶳偵搊傞偺偵壗張偺儖乕僩傪扝傠偆偑丄搊捀偱偒傟偽庤抜偼娭學側偄偲偄偆堄枴偺敪尵傪偝傟偰偄傞傛偆 偱偁傞偑丄僄儀儗僗僩偵搊傠偆偲偟偰丄柌偺拞偱壠偺棤偺嵒嶳偵搊偭偰僄儀儗僗僩搊捀偵惉岟側偳偲丄悂挳偝傟偰偼崲傞偺偱偁傞丅 傑偨丄埲壓偵巊梡偡傞帒椏丄幨恀偼帺暘偺暔埲奜偼丄嫋壜傕庴偗偢偵彑庤偵宖嵹偡傞帠傪偍嫋偟婅偄偨偄丅 寶梣偺庡惗嶻昳偑拑怓偺壯栚揤栚拑榪椶偱偁傞帠偼慜婰偟偨丅 梣愓偵偼氺偟偄悢偺摡曅偑嶶棎偟偰偄傞偑丄偦偺傎偲傫偳偼拑怓偺壯栚揤栚偺攋曅偲僒儎敨椶偺攋曅偱偁傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂丂丂丂 丂丂丂丂 嵍偺幨恀偼寶梣偱惗嶻偝傟偨拑榪偺戝敿傪惉偡丄拑怓偺壯栚揤栚拑榪丄塃偺幨恀偼嬧怓偺壯栚揤栚拑榪偱偁傞丅 拑怓偺壯栚偼懡偄偑丄嬧怓偺暔偼嬌傔偰婓偵惗傑傟偨傛偆偱偁傞偑丄桘揌揤栚傗梛曄揤栚偵斾傋傟偽懡偔巆偝傟偰偄傞丅 摉曽偱寶梣偺壯栚揤栚拑榪偺攋曅傪嵞從惉偟偰幚尡偟偨尷傝偱偼丄悽娫偱尵傢傟傞掱丄寶梣偺揤栚拑榪偼嬌抂側娨尦從惉 傪偝傟偨暔偱偼側偔丄拑怓偺壯栚偼從惉偺嵟廔抜奒偱偐側傝巁壔墛偵嶯偝傟偨暔丄嬧怓偵嬤偔側傞暔傕從惉搑拞偱堦搙婜 巁壔墛偵嶯偝傟丄偦偺屻丄嵟廔抜奒偱娨尦嶌梡傪庴偗偨暔偱偼側偄偐偲悇嶡偝傟傑偡丅 傑偨丄彂暔偵傛偭偰偼丄缰栻偑擇廳妡偗偝傟偰偄傞偲偺婰弎偑尒傜傟傑偡偑丄巹偺尒偨寶岬偺拞偵偼偦傟傜偟偒缰栻偺傕 偺偼堦偮傕偁傝傑偣傫偱偟偨丅 偍偦傜偔偼丄拑梞梣惢昳偺奃旐揤栚拑榪偲偺崿摨偱偼側偄偐偲巚傢傟傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂 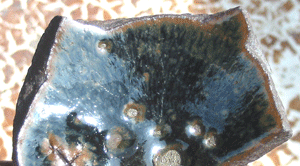 丂 丂 丂 丂 丂 丂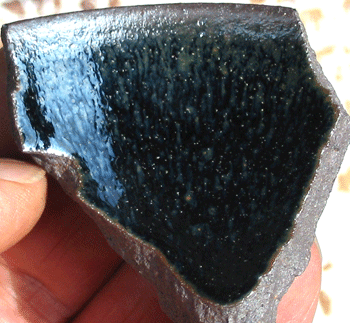 丂 丂傑偨侾俋俉侽擭戙偵拞崙偱峴傢傟偨寶梣偺敪孈挷嵏帪偵敪昞偝傟偨缰栻偺暘愅抣偼師偺傛偆側傕偺偱偟偨丅 堦椺傪梘偘偰偍偔帠偵偟傑偡偑丄悢廫庬椶偺僒儞僾儖偺抣偼偳傟傕偦傟傎偳嵎偺偁傞悢抣偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅 僇儕僂儉丗2.96亾丄僫僩儕僂儉0.09亾丄僇儖僔僂儉6.20%丄儅僌僱僔僂儉1.68亾丄儅儞僈儞0.65亾丄傾儖儈僫18.73亾 擇壙揝6.20亾丄堦壙揝1.69亾丄僠僞儞0.76亾丄儕儞巁1.25亾丄宂巁60.92亾 偍傛偦丄揝暘偼俇亾撪奜偺暔偑懡偔丄惉暘揑偵偼尰抧偺愒搚偵栘奃傪攝崌偟偨偩偗丄傕偟偔偼晽壔偺庛偄愒搚偺尦偺 傛偆側暔偵栘奃傪攝崌偟偨偩偗偱偼側偄偐偲偺悇應偑惉傝棫偮暔偱偡丅 傑偨丄尰抧偵偼恀偭敀側僇僆儕儞幙擲搚傗丄揤栚拑榪偵梡偄傜傟偨暔傛傝傕揝暘偺彮側偄擲搚傕偨偔偝傫桳傝丄偙傟 傜偼僒儎敨傗栚搚偵巊傢傟偰偄偨傛偆偱偡丅 寶梣偼偁偔傑偱傕柉梣偱偡偑丄姱偵傕廂傔偰偄偨帠傕抦傜傟偰偍傝丄崅戜撪偵偼乽嫙屼乿傗乽恑岬乿側偳偺暥帤偑崗傑 傟偰偄傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂 |
| 梛曄揤栚拑榪 揱彸偲柾曧 |
| 梛曄揤栚拑榪偵偼屆偔偐傜尵偄揱偊傜傟偨丄揱愢偺傛偆側傕偺偑懡悢懚嵼偟傑偡丅偦偺婔偮偐傪梘偘偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅 斾妑揑丄怴偟偄懎愢傕擖傟偰傒傑偟偨偑丄椺偊偽寣塼傪怳傝偐偗傞愢偵偼儔僗僞乕奊偺嬶偺尨椏偱偁傞價僗儅僗偑旝検偵 娷傑傟偰偄傑偡偟丄僞儞僌僗僥儞偱偼擑怓偺惎宍丄懡妏宍偺寢徎偑惗傑傟傞帠偼屆偔偐傜抦傜傟偰偄傑偡偟丄嬧偺奊偺嬶 偑儔僗僞乕偲偟偰巊偊傞帠傕屆偔偐傜抦傜傟偰偄傑偡丅 埥堄枴丄偳傟傕堦棟桳傞愢偺傛偆偵巚偊偰偒傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂 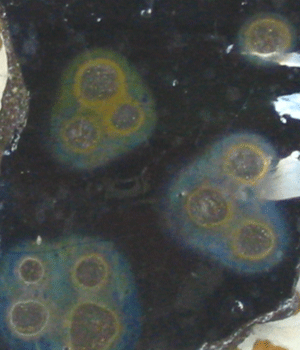 丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂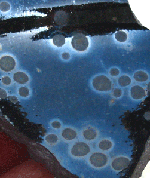 丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂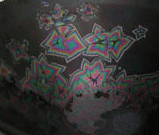 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬧偲墧偺奊偺嬶丂丂丂丂丂丂嬧偲墧偲價僗儅僗丂丂丂丂丂丂丂僞儞僌僗僥儞偺寢徎 丂傑偩傑偩丄偙偺懠偵傕怓乆側媄朄偱梛曄揤栚傕偳偒偼嶌傞帠偑弌棃傑偡偑丄偄傢備傞乽幨偟乿偲偼堘偄丄梛曄揤栚拑榪偺 丂斄栦柾條傪奊晅偗偡傞傛偆側帠偼丄怲傓傋偒峴堊傑偨偼乽奊晅偗梛曄揤栚晽拑榪乿偲偱傕昞婰偡傋偒偩偲巚偄傑偡丅 |
| 梛曄揤栚拑榪丂娤嶡 |
丂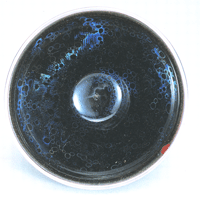 丂丂 丂丂 丂丂 丂丂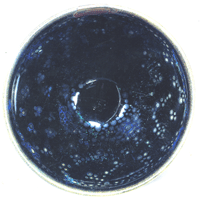 丂丂丂丂丂丂摗揷旤弍娰丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惷壝摪暥屔旤弍娰丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝摽帥棿岝堾 幨恀偼尵傢偢偲傕抦傟偨梛曄揤栚拑榪偺俁偮偱偡偑丄偙偺俁偮偺拑榪偺壗張傪尒偰巹払偼偙傟偑梛曄揤栚拑榪偩偲敾抐偟偰偄 傞偺偱偟傚偆偐丅 偦傟偲塢偆偺傕丄俁偮偺拑榪偺斄栦偺尰傟曽偼傛偔娤嶡偡傞偲丄偐側傝堘偭偰偄傞偺偵傕娭傢傜偢丄巹払偼偙偺斄栦偺弌偰偄傞 攝抲丄孮傟偛偲偵暲傇斄栦偺攝抲偐傜丄偙傟傪梛曄揤栚拑榪偩偲擣幆偟偰偄傞傛偆偱偁傞偐傜偱偡丅 堦偮堦偮偺斄栦偺弌曽偱丄摿挜揑側暔傪梘偘偰傒傑偡丅 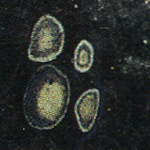 丂 丂 丂 丂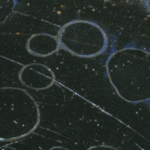 丂 丂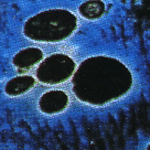 丂 丂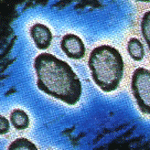 丂丂丂丂嘆丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘇丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘊丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘋丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘍 嘆拞怱偵墌忬偺斄栦偲偦偺廃埻偵儕儞僌忬偺椫偑偁傞傕偺偱丄擑嵤偼尒傜傟側偄傕偺丅 嘇墌忬偺斄栦偺傒偱嬧敀怓丄廃埻偵偼儕儞僌傗擑嵤偼傒傜傟側偄傕偺丅 嘊儕儞僌忬偺椫偺傒偱丄拞怱晹偼奜懁偺崟缰抧丄廃埻偺擑嵤偼尒傜傟側偄傕偺丅 嘋擑嵤偺傒偑懚嵼偟丄儕儞僌忬偺椫偼徚偊偰偍傝斄栦偼崟缰抧偲側偭偰偄傞傕偺丅 嘍拞怱偺墌忬斄栦偑嵼傝丄儕儞僌偼徚偊偐偐傝丄廃埻偵偼擑嵤偑奼偑偭偰偄傞傕偺丅 戝偒偔暘椶偡傞偲丄埲忋偺傛偆偵偩偄偨偄俆偮偺斄栦偺忬懺偺僷僞乕儞偵暘偗傜傟傞丅 偙偺傛偆偵暿屄偺夋憸偵暘妱偟偰傒傞偲暘偐傝傗偡偄偑丄梛曄揤栚偺斄栦帺懱偵偼條乆側僷僞乕儞偑懚嵼偡傞偑丄嫟捠揰偼 孮傟忬偵暲傫偱懚嵼偟偰偄傞偙偲偱丄偙傟偑梛曄斄栦偺堦斣偺摿挜偲傕峫偊傜傟傞丅 師偓偵摿挜偲偟偰丄挊偟偄偺偼偦偺擑嵤偲昞尰偝傟傞怓崌偄偱偁傠偆丅 尵梩偱昞尰偡傞帠偑擄偟偔丄幨恀偱偼暘偐傝偯傜偄偑丄嬧敀怓丄惵嬧怓丄偲偱傕昞尰偟偨傜椙偄傕偺偐丄尒傞妏搙偵傛偭偰 偦偺惵偔尒偊傞晹暘偑摦偄偰尒偊傞偐傜傗傗偙偟偄丅 傑偨丄岝慄偺摉偨傝嬶崌偵傛偭偰偼丄椢怓丄愒怓丄烌怓丄側偳偑嬐偐側偑傜尒偊傞堊偵丄傛傝怓嵤偑暋嶨偵姶偠傜傟傞丅 傑偨丄斄栦偼墌忬偲偟偐尵梩偑尒偮偐傜側偄偑丄偐側傝榗側傕偺偑懡偄丅 娙扨偵峫偊傟偽丄缰栻偐傜尰傟偨偺偐偳偆偐偼暿偵偟偰丄拞怱偵偁傞墿奃怓偺斄栦偑梈偗偰丄廃埻偵奼偑傞嵺偵儕儞僌忬傪 惉偟丄偝傜偵廃埻傊偲奼偑傞嵺偵枌偑敄偔側偭偰惵怓偑嫮偔姶偠傜傟傞傛偆偵側傞偐偺傛偆偵尒偊丄擑嵤偺斖埻偑峀偄売強 傎偳丄拞怱偺斄栦偼傏傗偗丄拞偵偼側偔側偭偰偄偰抧偺崟缰偵側偭偰偄傞売強傕偁傞丅 傑偨丄擑嵤偑慛傗偐偵弌尰偟偰偄傞応強丄峀偑傝偺戝偒側売強傎偳丄偦偺擑嵤偺宍忬偑柧傜偐偵丄壯栚忬偵側偭偰偄傞偑丄 偙傟偼丄壯栚揤栚偲偺娭楢傪巉傢偣傞偵廩暘側傕偺偩偲傕峫偊傜傟傞丅 傑偨丄棿岝堾偺梛曄揤栚偺拑偩傑傝晅嬤偱偺斄栦偼丄惷壝摪強憼偺桘揌丄戝榦偺偦傟偵嬤偄斄栦偲傕峫偊傜傟丄桘揌揤栚偲 偺旕忢偵嬤偟偄娭學傪傕姶偠偝偣傞偵廩暘偱偁傞丅 擔杮偵巆偭偰偄傞俁偮偺梛曄揤栚拑榪偩偗偱傕丄偙偺傛偆偵斄栦偺弌曽偑悢庬椶傕偁傞帠偼丄幚偼梛曄揤栚偲偄偆斄栦偼 傕偭偲丄條乆側僷僞乕儞偺忬懺偺斄栦偵側傞壜擻惈傪旈傔偰偄傞偲偼峫偊傜傟側偄偱偁傠偆偐丅 傓偟傠丄偦偆峫偊偨曽偑帺慠偱偁傠偆丅 怐揷怣挿偲嫟偵從幐偟偨梛曄揤栚拑榪偑丄偄偭偨偄偳偺傛偆側忬懺偺斄栦偺斄栦偺尰傟偨暔偱偁偭偨偐傪憐憸偟偰傒傞偺傕 柺敀偄丅 |
| 梛曄揤栚拑榪偲桘揌揤栚丄壯栚揤栚 |
    忋偺係偮偺揤栚拑榪偺幨恀偼丄嵍偐傜弴偵搶梞摡帴旤弍娰憼丄崻捗旤弍娰憼偺棤偲昞丄惷壝摪暥屔憼偱偡丅 俀枃栚偲俁枃栚偼摨偠拑榪偺棤偲昞偱偡丄偙偺拑榪偼娙扨偵尵偊偽昞懁偑桘揌揤栚偱棤懁偑壯栚揤栚偵側偭偰偄傑偡丅 侾俋俉侽擭戙偵敪孈挷嵏偺恑傫偩寶梣偺梣愓偺丄拑榪偺缰栻傕戀搚傕憡摉悢偺壢妛揑暘愅偑恑傔傜傟丄岞昞傕偝傟偰偄傑偡丅 傎偲傫偳偼壯栚揤栚拑榪偺攋曅偺暘愅偱偡偑丄桘揌揤栚偵娭偟偰偼柤屆壆戝妛偺柤梍嫵庼偱傕偁傝丄桞堦梛曄揤栚拑榪傪尠旝嬀偱娤嶡偟丄榑暥傕敪昞偝傟偰偄傞嶳嶈堦梇攷巑偑暘愅偝傟偰偄傑偡丅 偟偐偟丄桘揌偲壯栚偺椉幰偺暘愅抣偵嵺偩偭偨堘偄偼暘愅偝傟偢丄椉幰偺缰栻偑傎傏摨偠惉暘偺暔偱偁傞帠偑柧傜偐偵偝傟偰偄傑偡丅 昅幰傕埲慜庤偵擖傟偨丄梛曄揤栚偲摨偠傛偆側擑嵤偑俆mm妏掱搙偺嬐偐偵尰傟偨拑榪傪庤偵擖傟偰丄偦偺晹暘傪暘愅偟偨帠偑偁傝傑偡偑丄偦偙偐傜摼傜傟偨僨乕僞偲偟偰偼丄0.02亾偺僀僢僩儕僂儉偲丄摨掱搙偺儖價僕僂儉偑捒偟偄惉暘偲偟偰偼専弌偝傟傑偟偨偑丄偙偺掱搙偺暘検偱缰挷偵塭嬁傪梌偊傞偲偼摓掙峫偊傜傟傑偣傫丅 條乆側丅壔妛揑側暘愅抣偲晅偗崌傢偣偰傒偰傕丄乽壯栚揤栚偲桘揌揤栚偼摨偠缰栻偱偁傞乿偲峫偊偰娫堘偄偼側偄偱偟傚偆丅 偦偺摎偊傪丄忋偺崻捗旤弍娰偺揤栚拑榪偼擛幚偵暔岅偭偰偄傑偡丅 傑偨丄嵍偺搶梞摡帴旤弍娰偺桘揌揤栚偲丄惷壝摪暥屔偺桘揌戝榦偼丄梛曄揤栚拑榪偲摨椶偺梀怓岠壥偱偁傞丄惵敀偔尒偊傞晹暘偑摦偄偰尒偊傞岠壥傪帩偭偰偄傑偡丅 傑偨丄棿岝堾強憼偺梛曄揤栚拑榪偺拑棴傑傝晅嬤偺桘揌忬斄栦偲惷壝摪暥屔偺桘揌戝榦偺斄栦傕旕忢偵帡捠偭偰偄傑偡偟丄梛曄揤栚拑榪偺擑嵤晹暘偺宍忬偑壯栚偺宍忬偦偺傕偺偱偁傞帠側偳偐傜丄憤崌揑側敾抐傪偡傞偲偡傟偽丄乽梛曄揤栚偺缰栻亖桘揌揤栚偺缰栻亖壯栚偺缰栻乿偲峫偊偨曽偑丄擺摼偺偄偔傕偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 傕偪傠傫丄旝検側惉暘偺岆嵎偼偁傞偵偒傑偭偰偄傑偡丅 |
| 梛曄揤栚偺斄栦偼偄偐偵偟偰惗傑傟傞偐 |
| 丂梛曄揤栚拑榪偺斄栦偑偄偐偵偟偰惗傑傟傞偺偐丄彅愢偁傞帠偼婛偵婰嵹偟傑偟偨偑丄戝偒偔暘偗偰峫偊傞偲俁偮偺壜擻惈偑偁傞帠偵側傞偲巚偄傑偡丅 堦偮偼丄梣偺拞偺壗傜偐偺忬懺偱婲偒傞偲偄偆廬棃偐傜扤傕偑峫偊偰偄傞傕偺丄堦偮偼梛曄揤栚偺斄栦偦偺傕偺偑寢徎偱偁傞偲偄偆寢徎缰愢丄傕偆堦偮偑斄栦偺柾條傪恖堊揑偵昤偄偨偲偄偆愢丅 嵟屻偺愢傪彞偊傞曽偼斄栦偺柾條偑恖堊揑側攝抲偵巚偊傞偲峫偊傜傟偰偄傞傛偆偱偡偑丄巹偵偼摓掙偦偆偼巚偊傑偣傫偟丄傕偟偦偆偱偁傟偽丄傕偭偲検嶻偝傟偨敜偱偡偟丄傕偭偲堘偭偨栦條傗嬶徾揑側奊傪昤偔壜擻惈偑偁傞偲巚偊傞偺偱偡偑丄偦偺傛偆側暔偼懚嵼偟偰偄傑偣傫丅 傑偨丄奊晅偗愢傪彞偊傞曽偺拞偵偼丄拑榪偺撪懁偵偩偗斄栦偑偁偭偰丄奜懁偵柍偄偲偄偆帠傪偍偭偟傖傞曽傕偄傜偭偟傖偄傑偡偑丄偙傟偼娫堘偄偱偁偭偰摗揷旤弍娰強憼偺梛曄揤栚拑榪偵偼丄奜懁偵傕斄栦偑懡悢懚嵼偟偰偄傑偡丅 傑偨丄寢徎缰愢偵娭偟偰偼俁偮偺拑榪傪娤嶡偟偰傕丄斄栦偑寢徎偩偲巚偊傞晹暘偑慡偔尒偮偐傝傑偣傫丅 丂丂丂  丂 丂 丂 丂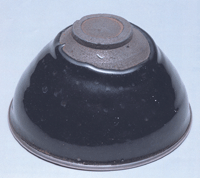 嵍偐傜弴偵丄棿岝堾丄惷壝摪丄摗揷旤弍娰偺梛曄揤栚拑榪偺奜懁偺幨恀偱偡偑丄摗揷旤弍娰強憼偺拑榪偵偼悢懡偔偺梛曄斄栦 偑婸偄偰偄傑偡丅 惷壝摪暥屔偺拑榪偵傕丄擇売強傎偳擑嵤偑尰傟偰偍傝丄棿岝堾偺拑榪偺奜懁偵偼栐栚忬偵擑嵤偵嬤偄婸偒偺嬝忬偺慄偑尒傜傟傑偡偑丄偙傟偼從惉拞偵婲偙傞尰徾偵傛偭偰尰傟偨暔偩偲峫偊傜傟傑偡丅 傑偨偙傟偼丄梛曄栦條偺敪尰偵怺偄娭學偑偁傞傛偆偱偡丅 梛曄揤栚拑榪偑奊晅偗揑媄朄偵傛偭偰惗傑傟偨偲偍偭偟傖傞曽偺懡偔偼丄偁偺晄巚媍側孮廜斄栦偑丄帺慠偺椡偱偼弌棃摼側偄攝楍偩偲偍峫偊偺曽偑懡偄傛偆偱偡偑丄師偓偵巹偑幚尡傪孞傝曉偟偨揤栚拑榪偵孮廜斄栦偑尰傟偨椺傪宖嵹偄偨偟傑偡丅 丂丂丂 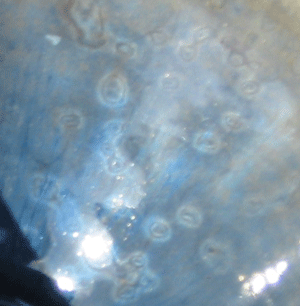 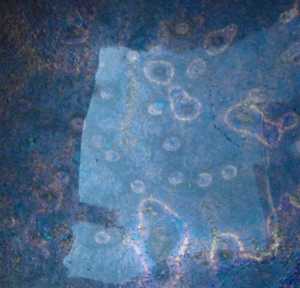   丂  丂 丂 丂 丂 丂 丂 丂 丂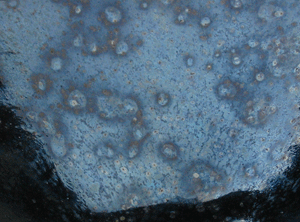 丂      丂丂  丂 丂 丂 丂 丂 丂  丂 丂 丂 丂 丂 丂 丂 丂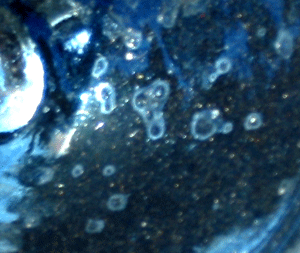 丂丂丂 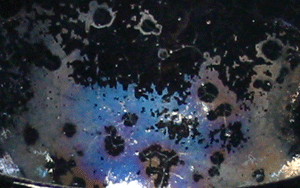 丂 丂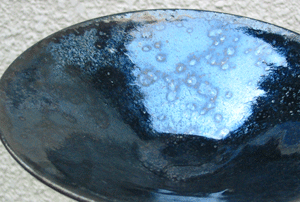 丂 丂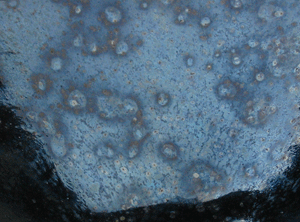 丂 丂 丂  丂 丂 丂 丂 丂 丂 戝検偺幨恀傪宖嵹偟偨偺偵偼栿偑偁傝傑偡丅 偮傑傝丄梛曄揤栚拑榪偺斄栦丄栦條偼恖堊揑側奊晅偗側偳偣偢偲傕丄梣偱從惉偡傞偩偗偱惗傑傟偆傞偺偩偲塢偆帠偱偡丅 偙傟傜偺拑榪偼丄柍榑巹偑梛曄揤栚拑榪偺栦條偑壗屘弌棃傞偺偐傪挷傋傞堊偵從偄偨暔偱偡丅 婎杮揑側缰栻偼偳傟傕寶梣偺攋曅偺暘愅抣偐傜摼偨悢抣偐傜挷崌偟偨丄扨弮側崟揤栚缰偲塢偊傑偡丅 偨偩丄岺嬈梡梣嬈尨椏傪挷崌偟偨暔偱偼側偔丄帺暘偱嵦庢偟偨娷揝搚愇尨椏傪巊梡偟丄帺暘偱從偄偨栘奃傪巊梡偟偰偄傑偡丅 偙傟傜偺幚尡偐傜暘偐偭偨帠偼丄梛曄揤栚偺斄栦偼寛偟偰擄偟偄暔偱偼側偔丄奊晅偗側偳偺嵶岺偐傜惗傑傟傞暔偱偼側偄帠丄 傑偨寢徎缰偱偼側偄帠偱偡丅 尨椏偺慖掕傗挷崌偑枹弉偱丄枹偩偵寶梣偺梣曄揤栚偲慡偔摨偠怓崌偄偺暔偼弌棃偰偄傑偣傫偑丄偙傟偼丄偦傕偦傕寶梣偱巊梡 偝傟偨暔偲慡偔摨偠尨椏傪巊梡偟側偄尷傝偼柍棟偱偁傞偲巚傢傟傑偡丅 偟偐偟丄孮廜斄栦偼偦傟偑柍偔偲傕惗傑傟傑偡丅 塢偊傞帠偼丄寶梣偺梛曄揤栚拑榪傕摨偠傛偆偵梣暟偒偩偗偱惗傑傟偨暔偱偁傞偲偺妋怣傪摼偨帠偲丄偁傞摿庩側忦審偑廳側傜側偄偲丄偙偺斄栦偼惗傑傟側偄堊偵丄寶梣偺傛偆側戝検偵揤栚拑榪傪從偄偨梣偱傕丄偍偦傜偔擔杮偵尰懚偡傞暔偲丄傕偟偁偭偨偲偟偰傕嬌彫悢偺暔偟偐梛曄揤栚拑榪偼從偐傟側偐偭偨偱偁傠偆帠丄傑偨擔杮偵尰懚偡傞俁偮偺梛曄揤栚拑榪偑丄摨偠梣暟偒丄偮傑傝侾夞偺梣暟偒偐傜惗傑傟偨壜擻惈偑崅偄帠側偳偱偡丅 傑偨丄尨嵽椏偑堘偆偲孮廜斄栦偑弌棃偨帪偵昁偢偟傕岝嵤偑廃埻偵尰傟傞栿偱傕側偔丄俁偮偺梛曄揤栚偵傕尒傜傟傞傛偆偵丄偄偔偮偐偺斄栦偺僷僞乕儞偑峫偊傜傟帠偱丄傕偟偐偡傞偲惷壝摪暥屔偺梛曄揤栚傛傝傕慺惏傜偟偄斄栦偑惗傑傟傞壜擻惈偑愽傫偱偄傑偡丅 偦傟偼丄怐揷怣挿偲嫟偵從幐偟偨梛曄揤栚拑榪偵旵揋偡傞暔偐傕偟傟傑偣傫丅 俁偮偺拑榪傪尒偰偄偰丄憐憸傪偨偔傑偟偔偡傞偲丄棿岝堾偺拑榪偑堦斣壏搙偑掅偔偁偑偭偨暔丄摗揷旤弍娰偺暔偑堦斣壏搙偺崅偄埵抲偵梣媗傔偝傟偰偄偨暔丄惷壝摪暥屔偺暔偑偦偺拞娫堟偵梣媗傔偝傟偰偄偨傕偺偱偁傠偆偲偺憐憸偱偡丅 堦弿偵惗傑傟偨梛曄揤栚拑榪偑丄傑偩悢榦偼偁偭偨壜擻惈偼旕忢偵崅偄偺偱偡偑丄堦偮偼怐揷怣挿偲堦弿偵從幐偟偰偄傑偡偟丄傕偟偐偡傞偲丄缰栻偑悅傟偰偟傑偭偨幐攕昳偑偁傝丄偦偺偆偪敪孈尰応偐傜攋曅偑敪孈偝傟傞壜擻惈偑廩暘偵偁傝偆傞偲巚偭偰偄傑偡丅 傑偨丄偙偺傛偆側梛曄揤栚柾條偑惗傑傟偨尨場偼丄摉帪偺梣暟偒偺幐攕偑尨場偩偲峫偊傞偺偑壢妛揑丄崌棟揑偩偲塢偊丄偦傟備偊偵偦偺屻丄偙傟偑從偐傟傞帠偑擇搙偲柍偐偭偨偺偩偲塢偆偺偑巹偺寢榑偱偡丅 丂丂丂丂丂丂丂 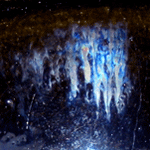 丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂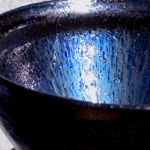 丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂 忋偺俁枃偺幨恀偼丄從偗偨壯栚柾條偑丄梛曄揤栚拑榪偺偦傟偲摨偠傛偆偵丄惵偔尒偊傞晹暘偑摦偄偰尒偊傞擑嵤忬偵側偭偨 傕偺偱偡偑丄壗屘偐偙傟偲孮廜斄栦偑摨帪偵惗傑傟傑偣傫丅 偙傟偑摨帪偵惗傑傟傞堊偵偼丄寶梣尰抧偺缰栻尨椏偲摨偠暔偑昁梫側傛偆偱偡丅 偦偆偱偡丄偮傑傝孮廜斄栦偑惗傑傟傞尨場偲丄撈摿偺擑嵤偑弌棃傞尨場偼暿乆偵峫偊側偗傟偽側傜側偄栿側偺偱偡丅 嵟屻偵側傞偑丄慜弌偺嶳嶈堦梇攷巑偺桳柤側榑暥偱偁傞丄乽梛曄揤栚乿偺偺拞偵傕丄僾儔儅乕嫵庼偐傜捀偄偨寶梣揤栚偺攋丂丂曅偺拞偵傕丄梛曄揤栚偺擑嵤偲椶帡偡傞惵巼怓偺岝嵤傪桳偡傞晹暘偑偁傝丄摿偵偙偺晹暘傪嶍偭偰暘愅偟偨偑偣偄傇傫偵曄丂丂傢傝偼側偔墧側偳偼娷傑傟偰偄側偐偭偨偲偺婰弎偑偁傝丄岝嵤偼墧缰偵傛偭偰惗偠偨傕偺偱偼側偄偲偟偰偄傞丅 傑偨丄暿偺売強偵偼丄斄揰偺廃埻偺缰偑幐摟寢徎偟偰偄傞偙偲丄斄揰偺廃埻偵惵巼怓偺岝嵤偑偁傞偙偲側偳偐傜尒偰恖岺揑丂丂偲偼峫偊擄偄丅 傑偨暿偺売強偵偼丄梛曄揤栚偺斄揰偲岝嵤偼摿庩偺尦慺偺懚嵼偵傛傞傕偺偱偼側偔丄捠忢偺寶岬偺缰偑摿暿偺忦審壓偭偱屌丂丂壔偟偨帪惗惉偟偨傕偺偱偁傠偆丄偲偺婰弎傕偁傞丅 傑偨暿偺売強偵偼丄惵巼怓偺岝嵤偑斄揰偺廃埻偵懡偄偙偲偼丄丄偙傟偑斄揰偺惗惉偲娭學偑偁傞偙偲傪帵偟偰偍傝丄栻昳偱丂丂缰傪恖岺揑偵晠怚偝偣偨偲偼峫偊擄偄丄偲偺婰弎傕偁傞丅 攷巑偑偙偺帪揰偱婛偵丄尰嵼偺摡寍奅偱峴傢傟偰偄傞傛偆側柾曧媄朄偺傎偲傫偳傪偛懚偠偱丄傑偨偙傟傜偺峴堊傪斲掕偟偰丂丂偄傞傛偆偱旕忢偵嫽枴怺偄 丂 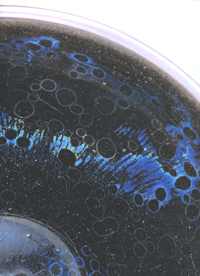 丂 丂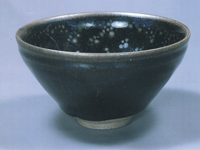 丂 丂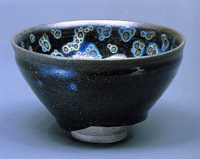 丂丂丂 丂丂丂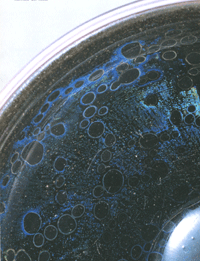 |